教授挨拶
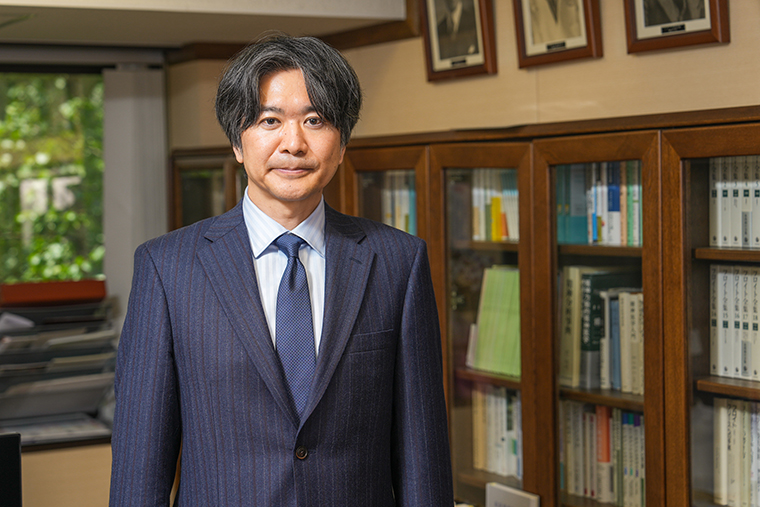
加藤 隆弘
TAKAHIRO A. KATO令和7年4月1日付で北海道大学大学院医学研究院神経病態学分野精神医学教室(北大精神医学教室)の第8代教授に着任いたしました加藤隆弘です。
北大精神医学教室は、1928年に開講され、初代教授の内村祐之先生から先々代の小山司先生、そして先代の久住一郎先生へと受け継がれてきた、百年近い歴史と伝統を誇る日本屈指の教室です。教育(人材育成)、研究(病態解明と治療法開発)、診療(医療の充実)の3本柱を基盤にして、精神医学と精神医療、さらには全人的医療の実践と発展に貢献してきました。
臨床では、統合失調症、気分障害、不安症、発達障害、摂食障害、認知症など、児童思春期から高齢者まで幅広い年齢層の精神疾患に対応し、全国唯一の大学病院付属司法精神医療センターを備えています。教育では、教室独自のクルズスを通じて、学生や研修医に対しマンツーマンで丁寧かつ体系的な指導を行っています。研究では、小山先生時代に完備されたウェットラボやヒト脳画像/脳生理活動測定体制を備え、基礎研究と臨床研究の両方に取り組むことができる全国でも数少ない教室の一つです。
教室の理念は、諏訪望先生(第4代教授)の「急がずに、休まずに」という言葉に象徴され、現在も受け継がれています。
教室では、精神科診断学の重鎮であられた山下格先生(第5代教授)が掲げた「診療に融け込む精神療法」の理念のもと、特定の学派に偏らず、日常診療の中で自然に展開される精神療法を大切にしてきました。こうした歴史の中で、先代の久住先生は以下のビジョンを掲げ、教室の発展に尽力されました。
- 基礎研究および臨床研究を基盤とした精神科医療の進展を通じ、精神障害者の障害克服に最大限寄与する
- 最高の精神科医療を提供できる多職種チームを構築し、
治療の拠り所となるエビデンスを世界に発信する過程を通じて、社会に貢献できる医師を育成する - 生物学的精神医学を基盤としつつ、力動的精神医学の視点を取り入れた治療を実践する
精神医学は人間のこころとその病を生物・心理・社会の側面から理解し、治療法を開発することで精神医療の発展に貢献する医学の一分野です。しかし、21世紀に入った現在でも精神疾患の病態解明は十分には進んでおらず、精神疾患・精神障害への偏見が根強く残っています。
私自身は鹿児島出身で、九州大学医学部を卒業後、九州大学精神科で様々な経験を積んでまいりました。薬物療法のみでは対応できない当時台頭したばかりのひきこもりや新型/現代型うつと呼ばれる新たな精神病理をもつ患者の治療に悪銭苦闘しながら、精神分析家・集団精神療法家になるための訓練を受ける一方、博士課程では抗精神病薬の脳内免疫細胞ミクログリアに関する基礎薬理研究に取り組みました。さらに、米国ジョンズホプキンス大学ではリバーストランスレーショナル研究手法を学び、帰国後は精神分析訓練を続けながら、ヒト血液由来ミクログリア様(iMG)細胞・血液バイオマーカーの開発や「ひきこもり」に関する世界初の専門研究外来の立ち上げ、地域支援体制の構築、国際共同研究の推進に携わってきました。
北海道と九州は日本の北端と南端に位置し、対極的な地理的条件を持ちながらも、自然豊かで自由を重んじる風土という共通点があります。この北の大地で、これまでの経験を活かし、教室員とともに創造的な臨床と研究を推進してまいります。当教室は北海道全域に関連医療機関を有しており、地域医療の発展に最大限貢献すべく精進いたします。広大な北海道の特性に配慮し、大学病院と地域医療機関との連携を強化するため、デジタル技術を活用した遠隔支援システムを導入し、生物・心理・社会モデルに基づく精神疾患およびひきこもりの支援拠点の創出を目指します。また、若手教室員の新しいキャリアパスを創出し、社会人大学院制度を活用して地域医療に貢献しながら臨床研究に従事し、博士号を取得できる体制を構築します。国際交流も加速させます。こうして、北大発の独創的な精神医療・精神医学モデルを世界に発信し、世界屈指の精神医学教室への発展を目指します。
最後に、当教室での研修や入局を検討されている皆さんへ。発達障害やひきこもり、ネット/ゲーム障害など、都市化やデジタル化社会を反映した新たな精神病理現象が台頭しており、未来の精神科医はこうした新たな課題にも臨機応変に対応する能力が求められます。皆さんが主役となり、未来の精神医学と精神科医療をともに創り上げていきましょう。北大精神科は、皆さん一人ひとりの個性や能力を最大限発揮し、「Think Globally, Act Locally」の精神で世界に羽ばたく精神科医を育成する場を提供します。皆さんとお会いできることを心から楽しみにしています。どうぞよろしくお願いいたします。
プロフィール
略歴
| 2000年 | 九州大学医学部卒業 精神科研修(九州大学病院、牧病院, 鮫島病院) |
|---|---|
| 2005-2008年 | 九州大学大学院医学系学府病態医学専攻(2008年早期修了:医学博士取得) |
| 2008-2010年 | 日本学術振興会特別研究員PD |
| 2010-2011年 | 九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点 特任助教 |
| 2011-2025年 | 九州大学精神科分子細胞研究室 グループ長 |
| 2011-2012年 | 米国ジョンズホプキンス大学精神科 日本学術振興会「日米脳」研究員(Akira Sawa Lab) |
| 2013-2017年 | 九州大学先端融合医療レドックスナビ研究拠点 特任准教授(脳研究ユニット長) |
| 2013年〜現在 | ひきこもり研究ラボ@九州大学(2025年4月「ひきこもり研究ラボ@九州&北海道」に改名) 代表 |
| 2017-2021年 | 九州大学病院精神科・神経科 講師 |
| 2021-2025年 | 九州大学大学院医学研究院精神病態医学 准教授 |
| 2025年4月1日〜現在 | 北海道大学大学院医学研究院神経病態学分野精神医学教室 教授 |
資格・専門医など
- 精神保健指定医
- 日本精神神経学会指導医・専門医
- 日本精神分析協会/国際精神分析学会認定・精神分析家(Psychoanalyst)
- 日本集団精神療法学会認定・グループサイコセラピスト
学会役員など
国内
- 日本精神神経学会(代議員)
- 日本精神分析学会(運営委員・医療問題委員長)
- 日本思春期青年期精神医学会(運営委員)
- 日本精神分析協会(会員)
- 日本集団精神療法(元理事)
- 日本生物学的精神医学会(評議員)
- 日本社会精神医学会(評議員)
- 日本うつ病学会(評議員)
- 日本神経精神薬理学会(評議員)
- 日本神経化学会(評議員)など
国際
- アジア精神医学会 AFPA(President Elect次期会長)
- 環太平洋精神科医会議PRCP(Director理事)
- 世界精神医学会 WPA(Urban Mental Health Section事務局長)
- 東アジア文化精神医学会(日本支部・事務局長)
- 日韓若手精神科医の会KJYPA(日本側世話人代表)
専門
- 気分障害
- ひきこもり
- 精神分析(力動精神医学)
- 集団精神療法
- 精神免疫学(ミクログリア)
- デジタル精神医学
