専門分野
- 気分障害
- ひきこもり
- 精神分析
- 力動精神医学
- 集団精神療法
- 精神免疫学
- デジタル精神医学

北大精神科は、百年の伝統を誇りに、革新を追求しながら、自由で活気ある雰囲気の中で活動しています。私たちは、北海道という特別な環境を最大限に活かし、最先端(cutting-edge)の臨床、研究、教育を推進しています。 入局をお考えの皆さんへ:私の好きな言葉は「Think Globally, Act Locally!!」です。この精神のもと、北大精神科では、若手医師が大きな夢を描き、それぞれの個性を存分に発揮できる環境を提供します。一流の臨床家・研究者になって、一緒に未来の精神医療・精神医学を切り拓いてゆきましょう。

北海道大学病院子どものこころと発達センターでは、包括的な児童思春期 精神科医療を行うとともに、将来の日本と北海道の児童思春期精神科医療を担う人材を養成することを目的としています。現在、社会的にも子どものこころの問題への注目が高まり、子どもの精神科医療は大きな転換期を迎えています。子どもへの包括的・有機的な介入・支援が必要になってきています。そのためには、子どもの精神科医療と研究にかかわる人材の養成が不可欠と考えられます。是非一緒にこの領域を発展させていきましょう。 今後、我が国の児童思春期精神科医療を充実していくために、そのような使命を共有できる情熱を持った若い力が当分野に加わってくれることを心から願っております。
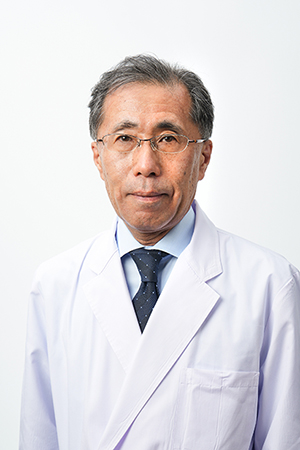
青年期の不安症や神経症の臨床と研究を主にしており、臨床症状評価尺度の開発や診療ガイドラインの作成などに取り組んでおります。新しい治療法の開発を一緒にしてみませんか?また、大学保健センターでは、学生に対する学校医、教職員に対する産業医も担当しております。病院臨床のみならず海外からの留学生や研究者も多くいる大学で、国際社会のダイナミズムを感じながらの学校精神保健、産業精神保健に興味関心のある方も大歓迎です。

私が勤務する司法精神医療センターは、大学病院が運営する全国唯一の医療観察法指定入院医療機関です。豊富なマンパワーで最強の多職種チームを作り、世界一患者さんがリカバリーする病棟を目指しています。さらに矯正施設に隣接する医療観察法病棟も全国唯一であり、矯正医療とも連携しています。司法精神医療、さらには精神医療の未来を変えるつもりでチーム全員で頑張っていますので、一緒に働きたいという方は是非ご連絡ください。
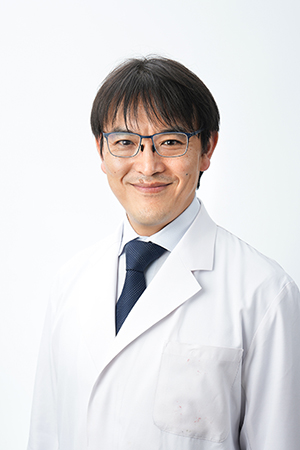
今精神科では、脳科学の視点からの精神疾患の理解が、着実に進んでいます。一方で、当事者と医療者の共同作業による治療の進行など、医療のあり方も進歩しています。最新の知見をアップデートし続ける脳科学の視点と、悩み、苦しみに寄り添う臨床からの視点を統合して、今提供できる一番良い医療を実現したいと思っています。 精神医学を志す皆様、脳科学と心への興味を両立させる北大精神科の医療を、ぜひ一緒に作り上げましょう。
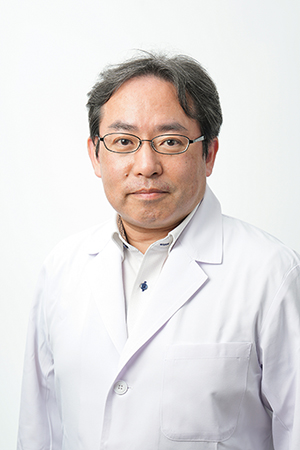
北大精神科は、様々なスタッフにより運営されている「学びの場」となっています。様々な年代の医師をはじめ、看護師、精神保健福祉士、作業療法士、心理士、薬剤師などのコメディカルスタッフと協力しながら、診療を進めますが同時に多くの学びがあります。また、研究に関する専門家も身近にいる環境で、求めれば様々な知識を得ることもできます。 私は、摂食症や大学生のうつ病の方など、若い年代の患者さんを中心に診療していますが、何よりも患者さんから多くのことを学んでいる、という感覚があります。北大精神科は、困っている人達に貢献しながら自分自身をも高めることができる、そんな素敵な場所になっていると思います。
自由に議論できる開放的な雰囲気の中で、医局員同士が協力し合いながら日々の業務に励んでいる様に惹かれ、現在に至ります。 臨床では精神疾患における急性期治療やリエゾンおよび災害医療に関心を持って日々業務に取り組んでいます。ご興味をお持ちの方は、お気軽にお声がけください。

こころの病気は、脳などの生物学的な要因だけでなく、気質や性格、成育環境、対人・社会関係といった心理・社会的側面が複雑に絡む現象です。当教室では、患者さん一人ひとりの個別性を重視した「見立て」を大切にしています。その見立てに応じて、山下格先生の提唱された「診療に融け込む精神療法」の理念を実践しながら、支持的精神療法・認知行動療法・精神力動的アプローチなどを柔軟に組み合わせた診療をしたいと考えています。 薬物療法に偏らない最適な個別医療を、ぜひ一緒に創り上げていきましょう。
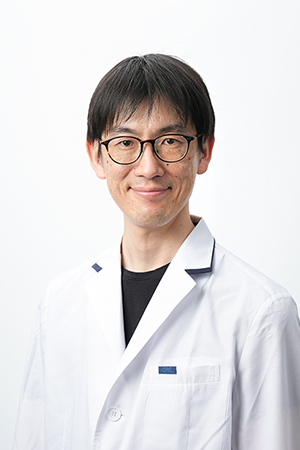
てんかんと心因性発作を専門的に診ています。社会との接点が大きい精神科医療の中でも、これらの疾患には特に生物・心理・社会の多角的な理解が欠かせません。難しい病態であっても、丁寧に解きほぐせば必ず良い方向にむかいます。 変化し続ける社会の中にあっても、変わらない人間の本質を大切にして、諦めず、地道に、泥臭く、人間らしくチャレンジしていきましょう。
児童精神科を受診する子どもが抱える問題は、勉強のこと、友人関係のことなど多種多様です。また、ご家族も子どもに関するいろいろな困りごと、悩みがあります。 診察では子ども、ご家族の困ったことをうかがい、病院でできる治療、サポートを行いつつ、時には、他職種、関係機関とも連携をとりながら、子どもにとって適切な支援を、医師として提供したいと考えています。

「自傷他害のおそれ」という言葉があります。人は精神が不調になると、自分を傷つけたり、他者を傷つけてしまうことがあり、そのような場合の判断に使う用語です。司法精神医学は、医学領域にとどまらず、法学、社会学、自殺学、犯罪学などと隣接し、学際的なアプローチでこれらの問題に取り組む学問です。 心を病んでしまった人が、いかにして苦境を脱し、再びこの社会で生きていけるようになるか。臨床・研究・教育を通して、日々その答えを探しています。

精神疾患の病態解明のためには、まず“正常な脳のはたらき”を理解することが不可欠です。私は、精神疾患の研究は脳科学研究そのものであると考えています。このような視点から、これまで正常な認知機能の神経メカニズムに着目し、動物モデルなどを用いた基礎研究を行ってきました。そして、得られた知見をいち早く臨床に還元し、患者さんの回復に結びつけたいと考えています。 北大精神科から発信する脳科学研究を、ぜひ一緒に取り組みませんか?
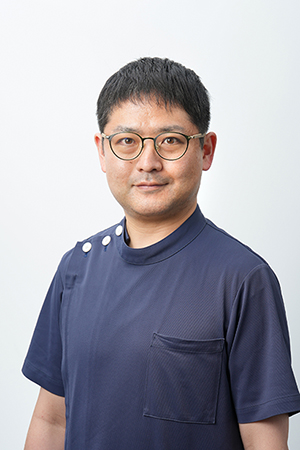
なんで私が精神科に、と感じる方は少なくないかもしれません。私が現在主に担当しているてんかん、認知症、リエゾン精神医学領域ではそのような患者様は多くいらっしゃいます。しかしいずれの領域においても精神医学的な評価や介入は不可欠です。患者様の思いを大切にしながら治療を進めて参ります。また上記領域に関心のある医学生、若手医師の皆さんは是非お声掛けください。 私たちと一緒に未来の精神医学を作り上げましょう。

精神疾患の患者さんで見られる認知機能の低下の評価法、介入法、神経基盤の研究を行っています。神経心理検査を用いた神経認知を行ったり、脳波の事象関連電位による神経生理学的な探索、MRIによる脳機能、構造の探索を行ってきました。認知機能障害の介入法である認知機能改善療法を北海道に最初に導入しました。 認知機能を通して、患者さんの機能的リカバリーの実現に関わる介入追求しています。
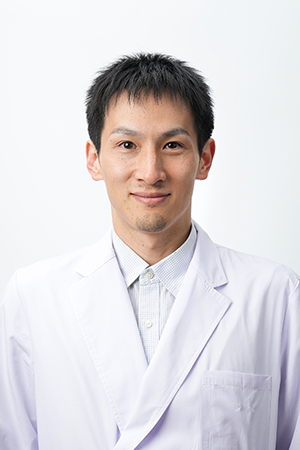
私は薬剤師としての業務に従事しながら、精神科領域に関わる臨床と基礎研究を、疾患や領域、分野を問わず幅広く取り組んでおります。臨床の現場では、些細な疑問や気づきが、目の前の患者さんを救う、あるいは医療の発展に繋がる研究の出発点となることがございます。 臨床の現場で疑問を感じることがございましたら、お気軽にお声がけいただけたら幸いです。皆さまの関心や疑問の解決に向けた研究の一助になれれば幸いです。